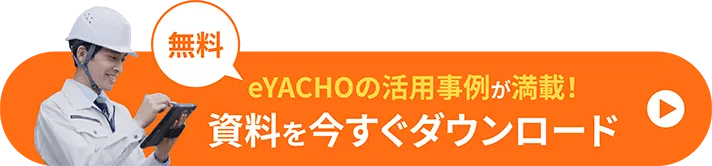【第5回】クラウド活用の勧め
クラウドの概念と歴史
クラウドとはクラウドコンピューティングの意味で、まるでコンピュータが雲の中にあるかのように、どこからでもどの端末からも利用することができる。
クラウドコンピューティングの概念は、1960年代にまで遡ることができる。この頃、アメリカの計算機科学者のジョン・マッカーシーは「コンピューティングはタイムシェアリング技術によってコンピュータの能力やアプリケーションを販売するビジネスモデルが出来るだろう」と予測していた。それがまさにクラウドコンピューティングの概念である。しかし、技術的な限界やインフラの不足により、その実現には数十年を要することになった。
2024年4月から「時間外労働の上限規制」が適用されたのはご存知の通り。これは働き方改革関連法案によるものだが、5年間の猶予期間を与えられていた建設業も本格的に取り組まねばならなくなった。この2024年問題は、建設業ばかりでなく物流・運輸業界・医療業界にも大きな影響を与えている。いずれも長時間労働が当たり前となっていた業界であって、建設業界はさらに従業員の高齢化や人手不足が畳み掛ける。
クラウドコンピューティングの基盤となったのは、1990年代のインターネットの普及であり、企業はウェブベースのアプリケーションを開発するとか、リモートでのデータアクセスを試みる様になった。2006年にGoogleのCEOであるエリック・シュミットが会議で「クラウドコンピューティング」という言葉を使ったことから、一般的な用語になった。
さらに同年にAmazonが「Amazon Web Services (AWS)」を立ち上げ、オンデマンドでのインフラストラクチャサービスを提供するという革新的なモデルを世に送り出した。
クラウドコンピューティングは進化を続け、現在ではSaaS(Software as a Service)、PaaS(Platform as a
Service)、IaaS(Infrastructure as a
Service)といった多様なモデルが利用可能になっている。これにより、企業はコンピュータを自前で所有する時代から、従量制で使う時代に大きな変化を遂げた。車を所有しないでカーシェアリングを活用するのと同じ概念である。

AIが描いたクラウドの概念
中小企業がクラウドを活用すべき理由
企業が自前でコンピュータを買い独自に情報システムを構築する場合、費用、時間、そして専門知識が必要である。しかし、これらの資源が限られている中小企業にとって、クラウドサービスを活用する選択肢は非常に魅力的である。
それぞれにメリット、デメリットがあるので事業の性質や戦略によって選択すべきであろう。
-
独自システムの開発
メリット:
完全なカスタマイズが可能で、特定の業務要件を満たすことができる データの完全な管理とプライバシーが確保されやすい。
競争優位性を強化するユニークな技術を活用して開発することができる。デメリット:
開発コストが非常に高額である。開発後の保守にも費用がかかる。
開発、保守、アップグレードに専門知識が必要である。
スケーラビリティが限られており、急速な成長への対応が難しい場合がある。 -
クラウドサービスの活用
メリット:
初期投資が少なく、コスト効率が高い。
スケーラビリティが高く、ビジネスの拡大に容易に対応可能。
技術的なメンテナンスはサービスプロバイダが行うため、専門知識が不要。
安全性と災害復旧機能が充実している。デメリット:
データの管理がプロバイダに依存するため、プライバシーの懸念がある場合がある。
カスタマイズの自由度が独自開発と比較して低い。
プロバイダの長期的な信頼性にリスクが付随する可能性がある。
クラウドサービスは一般に利用に応じて月額料金を払えばよいサブスクリプション方式が多いので、初期投資を軽減し、運用管理の負担も不要になる。また、格安で利用できるサービスも多く存在し、事業規模に応じた柔軟な運用が可能である。
自社の業務にあった情報システムが欲しいなら独自に構築するしかないが、スキルも必要だし、大きな費用が掛かる。知識やスキルがなく外部のベンダーに依存すれば、思い描くシステムはなかなか出来ない。
一方、出来ているシステムを利用するクラウドサービスは、利用する側の知恵で柔軟に活用することも可能になる。中小企業にとって作るか、使うかの判断は難しいものではない。
建設業向けのクラウドサービスやアプリ
建設の現場では生産管理のための様々な業務がある。品質管理、コスト管理、工程管理、安全管理、環境管理、情報管理などが主なものだが、多くは定型業務であることから可視化と標準化によってデジタルで効率を上げることが出来る。現場の社員は出来るだけ非定型業務に従事できる様にして、そのためのコミュニケーションと情報共有の環境を整える。
建設業向けのクラウドサービスには、労務・安全衛生管理書類であるグリーンファイルを作成・提出・共有できる歴史あるクラウドサービス「グリーンサイト」がある。作業員の入退場履歴もわかるので、入退場管理の効率化や建設キャリアアップシステム(CCUS)と連携させた情報管理もできる。
グリーンサイトのオプション機能に「ワークサイト」があり、作業予定・配置計画・重機管理・機械稼働実績管理・安全環境日誌など施工管理や情報管理をすることが出来る。
現場施工管理のためのアプリも様々なものが提供されている。写真管理や写真台帳作成に向いているもの、工程管理に向いているもの、日報や報告書作成に向いているもの、図面管理に向いているもの、タスク管理やファイル管理に向いているものなどそれぞれ特徴がある。

何が現場管理の課題になっていて、どんな現場業務を効率化したいかを検討し、無料で提供されているトライアルで機能や操作性を確認し、サポートを含めて導入した場合の年間コストを確認した上で導入すれば、多くの提携業務の効率化に役立つことは間違いない。
現場での雑多な帳票管理や写真管理、データ収集を効率化する「eYACHO」も評価が高く、リアルタイムで包括的な現場業務の情報管理と共有が出来る。
今回のコラムは、挿絵を含めて生成AIを活用して書いてみた。生成AIは特性や使い方さえ間違わなければ十分に実用レベルになっている。更なる効率化に向けて定型業務にも非定型業務にも生成AIを活用する時代になっていくだろう。