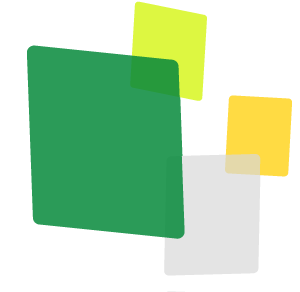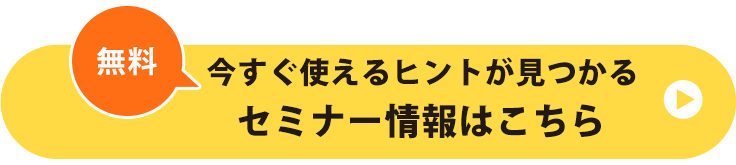日本の社会インフラを支える建設業界は、今、これまでにない大きな課題に直面しています。それは、熟練した技術者の高齢化による「技術継承」の問題です。若手人材の確保が難しくなり、現場のノウハウや知識の伝承がうまく進まない状況が続いています。このままでは、生産性や品質、安全性の低下が避けられません。ここでは、建設業の技術継承がなぜ課題となっているのか、その現状と根本的な理由を分析し、デジタル技術や仕組み化による新たな手法まで、現場力を持続的に育てるための道筋を具体的にご紹介します。
公開日:
建設業の技術継承とは?
持続的な現場力を育てる仕組みと新たな手法
建設業における技術継承の現状と課題
建設業界では、長年現場を支えてきたベテラン技術者の高齢化が進み、若手の入職者が減り続けていることが深刻な問題となっています。こうした状況は、現場での技術やノウハウの伝承を一段と難しくしており、従来の「見て覚えろ」といった方法だけではもはや限界を迎えているのが現実です。技術が十分に共有されず、特定の人に依存する「属人化」が進行すれば、重要な情報やノウハウが退職と同時に失われてしまいます。ここでは、建設業界の技術継承に関わる課題を深く掘り下げてみましょう。

少子高齢化と人材不測の影響
現在、建設業界全体で働く人の数は減少傾向にあります。特に技能者の高齢化が進み、国土交通省の調査によれば、60歳以上の技能者が全体の約4分の1を占めている状態です。さらに、将来を担う29歳以下の若年層は全体の12%ほどに留まっており、業界の将来を支える若手人材の確保がますます難しくなっています。このままいけば、今後10年以内に多くのベテランが一斉に退職期を迎えることが予想されており、業界全体で「技術者の崖」に直面するとされています。人材不足は、単なる人手の問題にとどまらず、日本の建設技術そのものが失われる「知識継承の危機」へとつながっています。
参考:国土交通省「建設業の人材確保・育成に向けた取組を進めていきます ~国土交通省・厚生労働省の令和7年度予算案の概要~(2024年12月27日)」https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo14_hh_000001_00249.html
「見て覚える」手法の限界
現場ではこれまでOJT(現場研修)や「見て覚えろ」という指導方法が主流でした。しかし、現在は次のような課題が表れています。
- ・OJTや現場任せの教育には時間と人材の余裕が必要
- ・教える人によって教え方や内容にバラつきが出やすい
- ・言語化・可視化されていない暗黙知が多い
- ・標準化や体系化が進まず、属人化しやすい
属人化によるリスク
ベテランの退職と同時に、その人にしかわからない作業や判断基準が失われることは、企業にとって大きなリスクです。業務への対応力や品質の維持が難しくなり、現場の力が低下する可能性が高まります。また、現場で働く新人がすぐに一人前になれず、技術の伝承や定着が遅れることで、長期的な組織力の低下を招くおそれもあります。
技術継承が進まない主な理由
現場監督の長時間労働の実態は、具体的なデータにもはっきりと表れています。一般的な現場監督の月間残業時間は、建設業界の中でも特に多くなっています。
教育・研修体制の未整備
多くの現場では、技術継承がいまだにOJTなど現場任せの教育に依存しているのが実情です。しかし、OJTだけでは指導者ごとに教え方や内容が異なり、若手が何をどのように学べば良いのかが明確になりません。座学と実技のバランスや、成長度を測る評価制度が不足しているため、若手が自分の成長を実感できず、モチベーションの低下や早期離職につながるケースも多く見られます。
マニュアルや教材の整備不足
技術をマニュアルとして明文化したり、動画や写真を活用した教材を用意したりする取り組みが進んでいない現場も多いです。紙のマニュアルが存在しても、内容が古かったり、分かりにくかったりする場合が多く、実際の作業に役立っていないこともあります。作業の「なぜ」を説明できる教材がないため、若手は理由を理解せずに手順だけを覚えることになり、応用力が身につきません。
多様な人材受け入れへの準備不足
これからの建設業界では、若手だけでなく女性や外国人、高齢者など、さまざまな人材を受け入れていく必要があります。しかし現場の教育体制や労働環境は、こうした多様な人材を受け入れる準備が十分とは言えません。たとえば外国人労働者に対する言語の壁、女性が働きやすい設備や環境の不足、長時間労働の習慣など、個別対応の難しさが人材の定着を妨げています。
デジタル技術で変わる技術継承の方法
従来のやり方では限界が見えてきた今、デジタル技術の活用によって技術継承のあり方が大きく変わりつつあります。動画や写真による記録、デジタルマニュアルの導入、AIやICT(情報通信技術)の活用など、さまざまな新しい取り組みが現場で始まっています。
動画・写真による記録と教材化
- ・熟練技能者の作業手順を動画で記録・保存
- ・現場の判断基準やコツを動画・写真付きで解説
- ・スマートフォンやタブレットで、いつでもどこでも学べる環境を実現
これにより、若手は何度も繰り返し学習でき、理解度も高まります。
デジタルマニュアルの活用
紙のマニュアルと違い、デジタルマニュアルは更新が簡単で、常に最新の手順や基準を全員で共有できます。現場で困ったときにはタブレットやスマートフォンで手順をすぐ確認でき、理解度のチェックや進捗管理もシステムで一元化することが可能です。これにより、技術や知識の標準化、教育の効率化が実現します。
| 特性 | 従来の手法 | デジタル手法 |
|---|---|---|
| 知識の形式 | 暗黙知・非言語 | 形式知・可視化 |
| 学習方法 | OJT・見て覚える | 動画・VR・デジタルマニュアル |
| アクセス性 | 現場限定・指導者依存 | クラウド・いつでもどこでも |
| 一貫性 | 指導者によるバラつき | 標準化・均一 |
| フィードバック | 非公式・遅延 | リアルタイム・データに基づく |
| 拡張性 | 1対1 | 1対多 |
組織的な仕組みづくりで継承を効率化
デジタルツールの導入だけでは十分ではありません。技術継承を持続的に進めるには、組織全体で育成や評価の仕組みを整え、個人の努力任せにしない体制づくりが不可欠です。
評価制度の整備で成長を「見える化」
若手が「自分の成長がわかりにくい」「今後どうなるのか不安」と感じて早期に辞めてしまうケースが増えています。これを防ぐためには、具体的なチェックリストや定期的な面談を通じて、技術の習得度を可視化し、段階的な目標設定やフィードバックを実施することが重要です。これにより、若手は自分が何を学べば良いかが明確になり、日々の業務に前向きに取り組むことができます。
段階別の教育プログラム
- ・基礎から応用までロードマップを作成
- ・ステップごとに学ぶ内容や達成目標を明確化
- ・指導方法のばらつきを減らし、効率的な技術伝承を促進
教育プログラムと評価制度がセットになることで、現場全体で一貫した成長サイクルが生まれます。
デジタル化・DXによる技術継承の効率化
最近では、ICTやAI、動画教材などを使った教育方法が急速に普及しています。これにより、遠隔地からの指導やクラウドでの情報共有が一般的となり、現場ごとのノウハウが組織全体で活かされる時代になりました。
ICT・AI・動画ツールの活用が広がる
AIやVR、ARなど最新技術を使えば、危険を伴う作業や高度な技能も仮想空間で安全に体験しながら学べます。AIは過去の災害データをもとに現場のリスクを自動で分析したり、教育計画や習熟度の管理もサポートします。また、現場の作業員がウェアラブルカメラを使ってリアルタイムで熟練技術者から遠隔指導を受けることもでき、必要なときに適切なサポートが受けられるようになりました。
参考:国土交通省「建設現場における『遠隔臨場』を本格的に実施します ~実施要領(案)の策定と事例集を発刊~(2022年3月29日)」 https://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo08_hh_000881.htmlデータ蓄積とナレッジシェアの促進
社内クラウドを使ってマニュアルや動画、過去の事例、トラブル時の対応記録などを一元管理することで、誰でも必要な情報をすぐに検索できます。これにより、特定の人に依存しない「集合知」が生まれ、現場の課題解決力や技術力が組織全体で高まります。こうした取り組みが、技術の属人化を防ぎ、持続的な現場力向上につながっています。
施工管理アプリeYACHOの主な機能と導入メリット
現場の技術継承や情報共有、業務効率化を進める上で、施工管理アプリ「eYACHO」は大きな効果を発揮しています。
- ・現場での書類作成や図面、写真、報告書の一元管理が可能です。
- ・音声や動画、手書き入力を使い、その場の状況や指示を正確に記録・共有できます。
- ・協力会社や職人同士でもデータをリアルタイムで連携できるため、連絡ミスや伝達漏れを減らせます。
- ・「遠隔臨場」やAIを使った安全対策サポートも充実しており、現場にいなくても段階確認や検査ができます。
- ・事例やオンラインセミナーも活用でき、導入時のサポートも手厚いです。
建設業の技術継承は「仕組み化」と「デジタル化」で変わる
建設業界が直面する技術継承の課題は、旧来のやり方だけでは解決できません。組織全体で明確な育成ロードマップや評価制度を整え、「仕組み化」すること、そしてデジタル技術を活用しノウハウを組織で共有する「デジタル化」を両輪で進めていくことが求められます。この二つの柱がそろうことで、現場力の底上げや人材の定着、働きやすい環境づくりが可能となり、企業の持続可能性も高まります。施工管理アプリ「eYACHO」などを活用しながら、貴重な現場ノウハウを次世代へ安心して引き継いでいく体制づくりを始めてみてはいかがでしょうか。
現場の技術継承・情報共有・業務効率化には施工管理アプリ「eYACHO」の活用がおすすめです。書類や写真、動画の一元管理や遠隔臨場など、デジタル化による継承強化をぜひ体験してください。詳しくは資料ダウンロード・無料セミナーへ。
▼資料ダウンロード https://product.metamoji.com/gemba/eyacho/document/ ▼無料セミナー https://product.metamoji.com/gemba/eyacho/seminar/