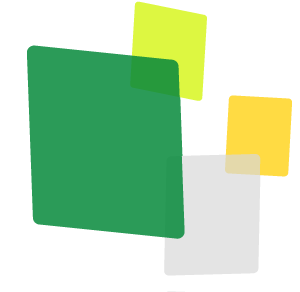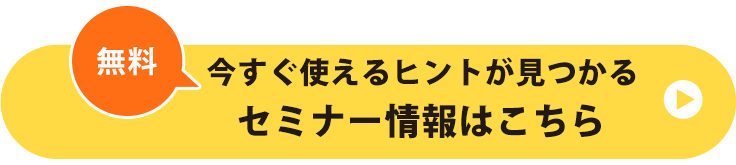現場で撮影する写真は、単なる記録ではなく、工事の進捗や品質、安全を客観的に証明するための大切な“証拠”です。しかし、「ただ撮るだけ」では、その価値を十分に活かすことはできません。この記事では、現場写真の役割や押さえておきたい撮影のコツ、整理・管理の工夫、最新ITツールの活用方法までを分かりやすく紹介します。今日から現場で役立つ実践的な知識を身につけて、信頼される現場づくりに役立てましょう。
公開日:
更新日:
現場写真の撮り方・コツを押さえて、
“使える写真”を残す方法
現場写真の役割と重要性
建設現場で撮影する写真は、単なる記録ではありません。
工事の進捗や品質、安全管理を“見える形”で証明するものであり、現場の信頼や関係者同士のスムーズな連携にも欠かせません。
現場写真の目的や役割を正しく理解することが、後々のトラブルを防ぐ大切なポイントとなります。
現場写真の役割と目的
現場で撮影する写真には、主に以下のような目的があります。
- ・工事の「証拠」として客観的な情報を残す
- ・契約や設計図通りに施工が進んでいることを示す
- ・各工程ごとの作業内容や進捗を証明する
- ・発注者への報告、中間検査や完了検査時の提出資料として活用
- ・出来高払いの根拠資料となる
- ・不具合やトラブル発生時の原因究明や責任の所在を明確にする手掛かりとなる
また、写真は現場にいない発注者や設計者、社内関係者とも「現地の状況」を視覚的に共有できるコミュニケーションツールとしても役立ちます。
現場写真で大切なのは、「誰が見ても分かる状態」で残すことです。プロジェクトに直接関わっていない第三者でも、「いつ・どこで・どのような工事が行われたか」が一目で分かるような写真を意識しましょう。
この意識が、品質保証やリスク管理にもつながります。
撮影するべきタイミングをイメージしておく
「使える写真」を残すためには、どのタイミングで何を撮影するか、事前にしっかり計画しておくことが重要です。
基本的な撮影タイミングは、以下の3つです。
| タイミング | 内容例 |
|---|---|
| 着工前 | 工事前の状況、基礎の地中埋設物など |
| 作業中 | 配筋、配管、設備設置などの作業工程 |
| 完了後 | 完成した状態、最終検査直前の全体確認 |
とくに、コンクリート打設前の配筋や壁内配管など、「あとから見えなくなる部分」は“今しか撮れない”という強い意識が必要です。
これらを撮り逃すと後から確認できなくなるため、必ず記録しておきましょう。
写真撮影のタイミングは、工事の進行スケジュールや各工程の“節目”に合わせて計画的に行うことが大切です。
日々の作業計画に「この作業が終わったら撮影する」と組み込むと、抜けや漏れを防ぐことができます。
分かりやすく伝わる現場の写真を撮るコツ
現場写真は、ただ撮るだけでは伝えたいことがきちんと残りません。
「誰が見ても分かる」写真を残すためには、いくつかの基本的なコツや撮影技術を押さえておくことが大切です。
5W1Hを写真と黒板で伝える
現場写真で特に重視すべきは、「5W1H」の情報がしっかり伝わることです。
これは、「いつ(When)・どこで(Where)・誰が(Who)・何を(What)・なぜ(Why)・どのように(How)」という6つの要素です。
ただ写真を撮るだけでは、すべての情報を伝えきるのは難しいため、「工事用黒板」や「ホワイトボード」を活用します。
黒板には、主に以下のような情報を簡潔に書きます。
- ・工事名・工種(例:○○ビル新築工事、基礎配筋工事)
- ・撮影箇所・測点(例:1F通り芯X1-Y2間)
- ・撮影年月日
- ・設計寸法・実測寸法
- ・施工状況(例:配筋検査状況)
黒板に書く文字は、写真になったとき誰でもはっきり読めるよう「大きく、濃く、丁寧に」書くのがポイントです。
また、太陽光や照明で文字が見えにくくならないように黒板の角度も工夫しましょう。
寸法を正確に伝える必要がある場合は、スケール(メジャー)を対象物にあてて一緒に撮影すると、数値の裏付けが簡単にできます。
複雑な部分の記録には、設計図の一部を「豆図」として黒板に貼り付けて撮影する方法も有効です。
このように、写真(映像情報)+黒板(文字情報)をセットで記録することで、写真1枚で「誰が見ても分かる」状態をつくることができます。

アングルと構図を決めて撮る
現場写真は芸術作品ではなく、「分かりやすく正確に伝える」ことが最優先です。
そのために重要なのがアングル(撮影角度)や構図(フレームの決め方)です。
まず基本となるのが「定点撮影」です。
同じ工事でも、施工前・施工中・完了後は、できるだけ同じ場所・同じ方向から撮影しましょう。
これによって、工程ごとの変化や進捗が分かりやすく記録できます。
定点撮影を行う際は、工事が進んでも全体が写るよう、少し引いた場所を選ぶのがコツです。

また、1つの事象については「全体写真」と「詳細写真」をセットで撮影します。
| 撮影の種類 | 内容 |
|---|---|
| 全体写真 | 対象物が現場のどこにあるかがわかる |
| 詳細写真 | 品質や寸法を確認したい部分に寄って撮る |
カメラのグリッド線を活用し、柱や梁、地平線などが水平・垂直になるよう意識すると、見やすく安定した写真になります。
不要な工具やゴミが写り込んでいないか、シャッターを押す前に必ず周囲を確認する習慣を持つことも大切です。
写真の「主役」以外の余計なものが入らないよう配慮することで、伝えたい内容がより鮮明になります。
編集・加工はNG!現場写真ならではの注意点
現場写真は「証拠」として扱われるため、一般的な写真のような加工や補正は原則禁止です。
特に公共工事では、このルールが厳格に定められているので注意しましょう。
明るさ補正やトリミングは避ける
現場写真は「ありのままの状態」で記録することが求められます。
明るさやコントラストの補正、不要部分のトリミング、画像の合成や文字・図形の挿入など、編集行為は一切NGです。
撮影した写真に問題があれば、その場で撮り直すことが唯一の対処方法となります。
これは、「デジタル写真管理情報基準」などでも明確にルール化されています。
不適切な編集は受入不可や再提出、検査での不承認といったリスクにつながるため、厳守しましょう。
- ・明るさやコントラストの調整は禁止
- ・不要部分のトリミングや合成も不可
- ・黒板情報をソフトウェアで修正するのもNG
写真の品質管理責任は撮影者にあるため、撮影後は現場で必ず確認し、問題があれば即再撮影する習慣を徹底することが大切です。
整理整頓と安全にも配慮する
現場写真は、工事の品質だけでなく、現場管理や安全意識の高さも映し出します。
写真を見る人は、被写体だけでなく背景や周辺の整理整頓状態からも多くの情報を読み取ります。
- ・ゴミや不要な資材、乱雑な工具が写り込まないよう撮影前に片づける
- ・整理された現場は、適切な管理がされている印象を与えやすい
- ・写真の主役が明確になり、見る人の理解も深まる
また、作業員が写る場合は、ヘルメットや安全ベストなど適切な保護具を着用しているか確認しましょう。
背景に安全規則違反が写り込んでいると、会社や現場のリスクにつながる可能性があります。
写真は「現場の監査記録」としても機能するため、撮影前のひと手間が信頼性を大きく左右します。
参考:国土交通省「デジタル写真管理情報基準」 https://www.mlit.go.jp/tec/content/001596260.pdf 参考:国土交通省「営繕工事写真撮影要領 令和5年版(2023年3月1日)」 https://www.mlit.go.jp/gobuild/content/001589800.pdfスマホやタブレット・アプリを活用して効率よく管理できる
近年は現場のIT化が進み、スマートフォンやタブレット、専用アプリを使った現場写真の管理が一般的になっています。
これにより、撮影や整理、共有などの業務効率が大幅に向上しています。
電子黒板やクラウドストレージを使って業務効率化
スマートフォンやタブレットは、高性能カメラを搭載しており、現場の記録用としても十分な機能を持っています。
画面が大きいため、撮ったその場で写真をしっかり確認でき、撮り直しもすぐ対応可能です。
専用アプリの電子黒板機能を使えば、物理的な黒板を持ち運ぶ手間が減り、手書きによるミスや読みづらさも防げます。
アプリ内にテンプレートを用意しておけば、数回のタップで黒板情報付きの写真を撮影でき、作業が格段にスムーズです。
さらに、多くのアプリはクラウドストレージと連携しています。
撮影した写真は自動的にクラウドに保存されるため、データ紛失のリスクが減り、遠隔の関係者ともリアルタイムで情報共有ができます。
| IT活用のメリット | 内容 |
|---|---|
| 電子黒板機能 | 手書きミスが減り、文字もはっきり記録できる |
| クラウド保存 | データ消失リスクが減り、共有も簡単になる |
| その場で撮影・整理・確認 | 現場から離れずに一連の作業が完結する |
写真台帳や報告書作成も自動化できる
従来は、撮影した写真を事務所で一枚一枚整理し、台帳や報告書を手作業で作成していました。
ですが、最近の工事写真アプリや管理アプリでは、台帳や報告書の自動作成機能が充実しています。
電子黒板で記録した写真には、工種や場所、寸法などの情報がテキストデータとして紐付いており、アプリが自動でフォーマットに沿った台帳を作成してくれます。
AI機能を搭載したアプリなら、写真の内容(例:「配筋」「型枠」など)を自動で仕分けし、状況説明も自動生成してくれるものもあります。
こうしたツールを使えば、事務作業の時間を大幅に減らし、現場担当者がより本質的な管理業務に集中できるようになります。
撮り忘れ防止&データ整理の工夫で業務ミスを防ぐ
どんなに良い写真を撮っても、「必要な写真が撮り忘れられていた」「データが行方不明になった」という状況では意味がありません。
撮影とデータ管理の両面で「抜け・漏れ」を防ぐ仕組みを構築しておくことが、現場の信頼性を高めるポイントです。
チェックリストやスケジュールで撮り忘れ防止
工事写真の撮り忘れは、後から取り返しがつかない重大なミスに直結します。
これを防ぐには、「チェックリスト」や「撮影計画書」を活用するのが効果的です。
- 取り忘れ防止の工夫例
- ・何をいつ撮るか、計画書・リスト化
- ・工程表と撮影タイミングを紐付ける
- ・撮影担当者を明確にする
- ・現場チームで重要性を共有する
チェックリストを作成し、「どこで・何を・いつ撮影するか」を事前に明記します。
撮影担当者を決めておくと、「誰かが撮るだろう」という曖昧な状態を防げます。
また、現場の朝礼などで「なぜこの写真が必要か」をチーム全体に共有し、協力体制を作ることも重要です。
データのバックアップと整理を徹底
写真データは工事の成果を証明する重要な資産です。
万が一のトラブルに備え、データの保全と整理のルールをしっかり決めておきましょう。
- ・データはクラウドや会社サーバー、外付けHDDなど複数の場所に保存
- ・「二重・三重バックアップ」が基本
- ・フォルダ分けやファイル名ルールを事前に決めておく
たとえば社内管理用には「工事名→工種→場所→日付」といった階層でフォルダを作成し、ファイル名は「日付_工種_内容.jpg」と一貫性を持たせておくと、後から目的の写真を素早く探せます。
ただし、公共工事の電子納品においては、「デジタル写真管理情報基準」でフォルダ構成や命名規則が細かく定められています。
納品データはPHOTOフォルダ直下のPICまたはDRAに保存し、階層分けはできません。社内運用と提出仕様を混同しないよう注意しましょう。
このような整理ルールを全員で共有し、実際に運用することで、必要な写真をすぐに取り出せる体制が整います。
参考:国土交通省「デジタル写真管理情報基準」 https://www.mlit.go.jp/tec/content/001596260.pdf現場写真を活かして、現場の信頼と品質アップにつなげよう
正確で分かりやすい現場写真は、工事の品質や安全管理を“見える化”する強力な手段です。
「誰が見ても分かる写真」を残す意識を持ち、5W1Hや黒板活用、定点撮影、全体+詳細写真のセット撮影など、基本を徹底しましょう。
また、編集禁止のルールや整理整頓・安全意識も守り、信頼性の高い写真を提供することが、発注者や協力会社からの評価につながります。
スマートフォンや専用アプリなどITツールを積極的に取り入れれば、写真整理や台帳作成の負担が減り、本来の管理業務に集中しやすくなります。
今日からできる小さな工夫やルール作りを積み重ねることで、ミスや手戻りのない現場づくりを実現し、担当者としての信頼度も大きく向上します。
現場写真を戦略的に活用し、現場全体の品質とチームの信頼を高めていきましょう。
現場写真の管理、撮影から台帳まで「eYACHO」で完結
eYACHO(イーヤチョウ)は、電子小黒板を利用した工事写真撮影を行う機能を搭載しています。
電子小黒板つきの工事写真撮影、写真の自動整理と工事写真台帳の作成、J-COMSIA/JACIC準拠の電子納品に対応。
チャットやクラウドとも連携し、現場から離れずに共有・報告まで完結できます。